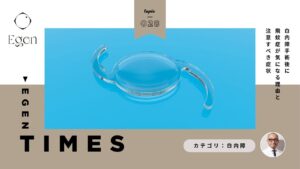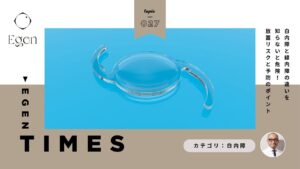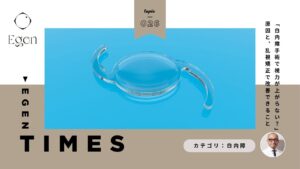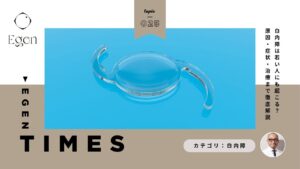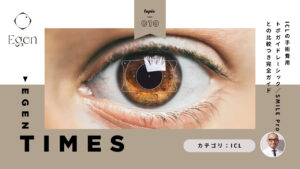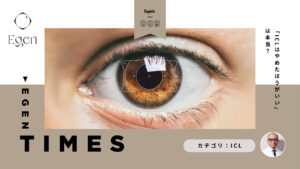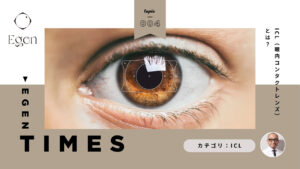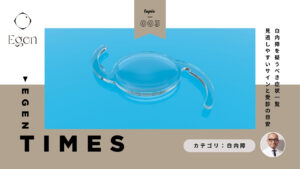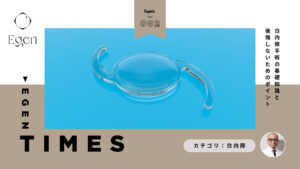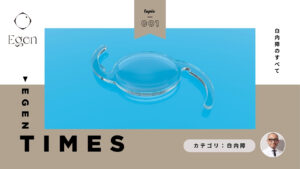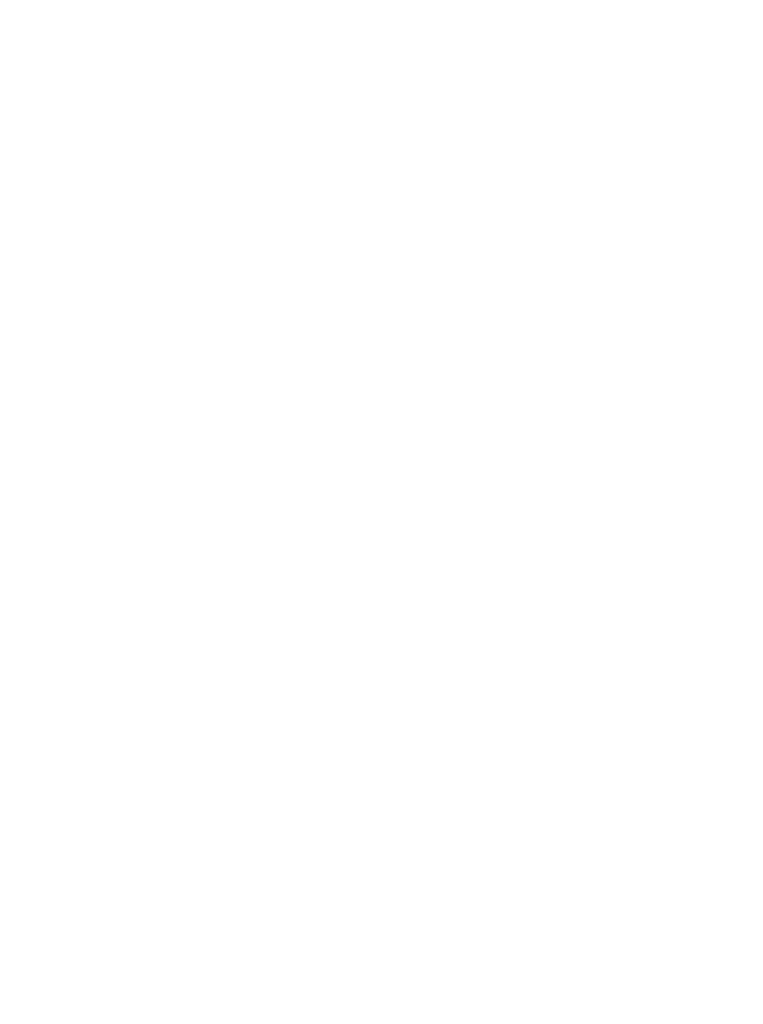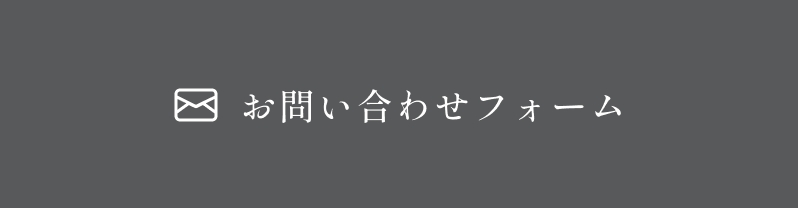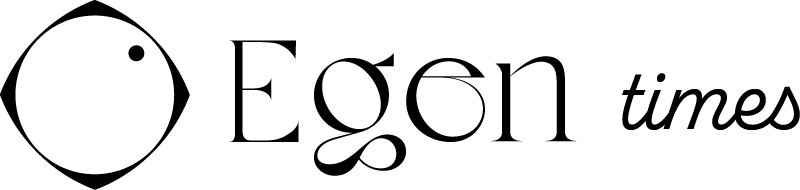白内障手術は、視界の濁りを取り戻し、生活の質を大きく向上させる有効な治療です。
しかし「痛みはあるの?」「費用は?」「どのレンズを選べばいい?」など、不安や疑問はつきもの。この記事では、手術の仕組みから費用・保険制度、術後の経過、起こりやすいトラブルと対策まで、実際の患者さんが知っておきたいポイントを一つひとつ丁寧に解説します。
白内障手術とは?

白内障手術は、濁った水晶体を取り除き、人工の眼内レンズ(IOL)に入れ替えることで視力を回復させる治療です。片眼あたりの手術時間は10〜20分程度で、多くの方が日帰りで受けています。
手術の目的と効果
白内障は、水晶体が濁ることで視界がかすんだり、まぶしさを感じたりする病気です。眼鏡をかけても視力が十分に出にくくなり、生活に不便が生じます。
白内障手術は、この濁った水晶体を人工の眼内レンズに入れ替え、明るく鮮明な視界を取り戻すことを目的としています。
実際に手術を受けた方からは、次のような変化が多く報告されています。
- 視界が全体的に明るくなる
- 色がより鮮やかに見える
- 眼鏡への依存が減る
- 読書や運転、買い物など日常生活が快適になる
手術そのものは片眼で10〜20分程度で終わり、多くの場合は日帰りで受けられます。
手術の適切なタイミング
白内障は「すぐに手術が必要な病気」ではありません。しかし、生活の質に影響が出てきた段階が手術を考えるタイミングです。
たとえば、眼鏡を変えても視力が出にくい、夜間の運転でライトがまぶしく感じる、新聞やスマホの文字が読みづらい、階段や段差が見えにくくつまずきやすいといった症状が目安になります。
症状が軽度であれば、すぐに手術を受けなくても、生活上の工夫で快適さを保てることがあります。
| 工夫の例 | 効果 |
|---|---|
| 眼鏡の度数調整 | 視力低下を一時的に補う |
| サングラスや遮光眼鏡 | まぶしさを和らげる |
| 室内照明・読書灯の活用 | 見やすさを確保 |
| デジタル機器の文字サイズ変更 | スマホやPCが読みやすくなる |
こうした工夫を取り入れることで、見え方と生活の質のバランスを整えながら、自分にとって最適な時期に手術を受ける判断ができます。
白内障手術の流れと所要時間

白内障手術は短時間で行える安全性の高い手術ですが、当日の流れや所要時間、痛みの有無など、実際のイメージがわからず不安を感じる方も少なくありません。ここでは、手術当日のスケジュールから具体的な所要時間、痛みの程度、さらに両眼を同日に手術できるかどうかまで、わかりやすくご説明します。
手術当日の流れ
白内障手術は日帰りで行われることが多く、全体の滞在時間はおおよそ1時間半程度です。
当日の流れは次のようになります。まず来院して受付を済ませた後、点眼によって瞳孔を広げ、術前の最終確認を行います。その後、手術室に移動して実際の手術を受けます。手術が終わったら15〜30分程度休憩し、医師から術後の説明を受けて帰宅するという流れです。
視力を回復させる手術の仕組み
白内障手術は、濁った水晶体を取り除き、人工の眼内レンズに置き換えることで視力を回復させます。
手術のステップをまとめると、
- 角膜(黒目のふち)に2〜3mmの小さな切開を入れる
- 水晶体嚢の前面を丸く開ける
- 濁った水晶体を砕いて取り出す
- 眼内に人工レンズを挿入し、固定する
という流れになります。現在はほとんどの施設で「超音波手術(Phaco法)」が標準的に行われています。
手術方法の違い
手術には2つの代表的な方法があります。
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| 超音波手術(Phaco法) | 超音波で水晶体を砕いて吸引する標準的手法。多くの施設で行われ、安全性が高い。 |
| フェムトセカンドレーザー手術 | レーザーで角膜切開や水晶体分割を自動で行う。組織への負担が少なく、見え方の安定性が高い。 |
フェムトセカンドレーザーは1兆分の1秒単位の精度で照射されるため、切開や核分割を非常に正確に行うことができます。その結果、術後の再現性や安全性が高まり、角膜やチン小帯へのダメージを軽減できるのが特長です。
所要時間と痛みの程度
片眼の手術時間はおよそ10〜20分です。点眼麻酔を使うため、メスや器具が入っても痛みはほとんどなく、圧迫感や光のまぶしさを感じる程度にとどまります。不安が強い方には、希望に応じて軽い安定剤を使用することもあります。
日帰り手術と両眼手術の進め方
白内障手術は原則として日帰りで可能です。高齢の方や持病を持つ方でも、多くの場合は外来で安全に受けられます。
ただし、両眼を同じ日に行うことは少なく、通常は1〜2週間ほど間隔をあけて片眼ずつ行います。これは、1つ目の眼の回復具合やピントの合い方を確認したうえで、もう一方の眼の設計に反映させるためです。予期せぬ炎症や眼圧上昇があった場合に備え、片眼ずつ進める方が安全性も高くなります。
★当院の特長
当院では、手術の安全性と術後の見え方の質を最優先に考え、「フェムトセカンドレーザー白内障手術(FLACS)」を導入しています。
一般的に、このレーザー手術を行う場合は別途数十万円の追加費用がかかるクリニックが多いですが、当院では「最高の機器を使うことが、患者さまの最良の結果につながる」という信念のもと、選定療養(多焦点レンズ)の手術において、レーザー使用料をいただかずに標準で行っております。(※クリニック側がコストを負担するサービスとして提供)
1兆分の1秒単位で制御されるレーザーを使用することで、手作業よりも圧倒的に正確で、眼への負担が少ない手術が可能になります。 「費用を気にして安全性を妥協してほしくない」という想いから生まれた、当院独自の体制です。
※なお、単焦点レンズをご希望で、かつこのレーザー手術を受けたい場合は、制度上「自由診療」でのご案内となります。詳しくはお問い合わせください。
白内障手術は短時間で終わる安全性の高い手術ですが、一人ひとりの眼の状態や生活スタイルに合わせた設計が重要です。手術を「受ける」だけでなく、「どう見えるようになりたいか」を医師と共有することが、満足度の高い結果につながります。
挿入する眼内レンズの種類と選び方

白内障手術では、濁った水晶体の代わりに「人工の眼内レンズ(IOL)」を挿入します。どのレンズを選ぶかによって術後の見え方や眼鏡の必要性が大きく変わります。当院では、単なるレンズ選びではなく、焦点距離や乱視矯正、ライフスタイルとの相性までを考えた「視機能設計」として、患者さまと一緒に最適なレンズを決定します。
レンズの主な種類
眼内レンズは大きく三つに分けられます。それぞれの特徴を理解して、自分の生活に合うタイプを選ぶことが大切です。
単焦点レンズ
1か所にピントを合わせるシンプルなレンズで、最も自然で鮮明な見え方が得られます。1か所とはいえ、合わせた焦点からある程度手前まではピントが合います。ピントが合う距離は、焦点をどこに合わせるかによって変わることには注意が必要です。遠方・中間・近方(∞、2m、1m、70cm、50cmから選択が可能)のいずれかに焦点を術前に設定し、それ以外の距離を見る際には眼鏡が必要です。保険診療が適用され、乱視矯正付き(トーリックレンズ)も同様に保険で対応できます。
近年はプレミアム単焦点とうたう眼内レンズが登場しておりますが、当院では若干コントラストが悪くなることと引き換えに得られる焦点深度の広がりが非常に限定的と考えており、取扱いはしておりません。
EDOF(焦点深度拡張型)レンズ
遠方から中間距離まで、連続的にピントが合う設計です。たとえば「運転からパソコン作業まで」を裸眼でカバーしたい方に向いています。コントラスト感度や夜間の見え方は単焦点に近く自然ですが、近くの細かい作業(読書やスマホ)は少し手を伸ばせば可能ですが、眼鏡が必要になることがあります。選定療養で対応します。
多焦点レンズ
遠・中・近の複数の距離にピントが合うため、眼鏡をほとんど使わずに生活できる可能性があります。回折型(3焦点)や屈折と回折を組み合わせたハイブリッド型などがあり、近距離まで幅広く対応。ただし、夜間に光がにじむ「ハロー・グレア」やコントラスト低下を感じる場合があります。選定療養または自由診療です。
種類別比較表
| 項目 | 単焦点レンズ | EDOFレンズ | 多焦点レンズ |
|---|---|---|---|
| ピント範囲 | 遠方か、中間か、近方 | 遠方〜およそ50cm | 遠・中・近に分散 |
| 眼鏡の必要性 | 距離に応じて必要 | 近方は必要なことあり | ほとんど不要 |
| 見え方の自然さ | ◎ | ○(単焦点に近い) | △(ハロー・グレアの可能性) |
| コントラスト感度 | 高い | 高い | やや低下傾向 |
| 夜間の運転 | 快適 | 多くの方が問題なし | まぶしさを感じる場合あり |
| 保険適用 | ○ | 選定療養 | ×(選定療養/自由診療) |
レンズ選びのポイント
「どのレンズが一番良いか」は人によって異なります。当院では次の観点から最適なレンズを一緒に検討します。
- 見たい距離の優先度
運転や外出が多いなら遠方重視、パソコンや料理をよくするなら中間重視、読書や手芸を楽しむなら近方重視など、日常生活の中心を考えます。 - 眼鏡へのこだわり
眼鏡使用に抵抗がなければ単焦点で十分。裸眼で過ごしたい方はEDOFや多焦点も候補になります。 - 夜間の見え方
夜間運転をよくする方やコントラストを重視する方は、ハロー・グレアが少ない単焦点やEDOFが向いています。
眼内レンズは「単焦点」「EDOF」「多焦点」の3タイプ。それぞれに利点と注意点があります。生活スタイルや見え方の希望、眼鏡の使用頻度を考慮し、医師と相談しながら自分に合ったレンズを選ぶことが、手術後の満足度を高めるポイントです。
麻酔・痛み・リスクについて

白内障手術を前に、「怖い」「眠れない」と感じるのは自然なことです。多くの方が抱く不安の多くは、実際に起こることよりも「未知への想像」から生まれます。手術の実際を知ることで、その不安は大きく和らぎます。
麻酔方法と痛みの実際
白内障手術では、目薬による点眼麻酔を使用します。注射は不要で、手術中に強い痛みを感じることはほとんどありません。
「まぶしい」「軽く押されるような感覚」を覚える程度で、痛みを訴える方はまれです。
不安が強い場合は、希望に応じて安定剤(緊張を和らげる薬)を併用できますので、遠慮なく相談してください。
恐怖心を軽くするために
「手術中に眼が動いたら?」「医師の体調は大丈夫?」という心配もよく聞かれます。
手術中は医師が声をかけて眼の動きを丁寧に誘導し、術者自身も体調管理を徹底して万全の状態で臨みます。
どんな疑問でも事前カウンセリングで説明しますので、不安は一つずつ解消していただけます。
大切なのは、「信頼できる医師に任せる」と決めたご自身の判断を信じることです。
合併症とその対策
白内障手術は非常に安全性が高い手術ですが、ごくまれに合併症が起こる可能性があります。代表的なものと対策は次の通りです。
| 合併症 | 内容 | 対策 |
|---|---|---|
| 眼内炎(感染) | 術後の炎症 | 抗菌薬で予防・早期治療が可能 |
| 眼圧上昇 | 一時的に眼圧が高まる | 点眼薬でコントロール |
| 後発白内障 | 数年後に再び濁る | レーザー治療で改善 |
| チン小帯断裂・水晶体嚢破損 | 手術中の偶発症 | その場で安全に処置 |
| 網膜剥離 | 特に強度近視でまれに発症 | 早期治療で視力回復が期待できる |
事前の精密検査と万全の管理体制により、これらのリスクは最小限に抑えられます。
失明のリスクについて
「手術が失敗して視力が出ないのでは」と心配する方もいますが、重大な失明は極めてまれです。
ただし、網膜疾患(加齢黄斑変性や糖尿病網膜症)、視神経の障害(緑内障)、強い乱視や角膜のゆがみなどがある場合は、視力回復に限界があることがあります。こうした場合は、術前検査で結果を説明し、見え方の限界を共有したうえで手術を行います。
明るい未来を想像して
白内障手術の目的は、ただ「濁りを取る」だけではありません。「見えるようになった自分」を想像してみてください。
・ぼやけていた本の文字がはっきり読める
・ゴルフボールの行方を目で追える
・孫と芝生で青空を楽しむ
・テレビや映画の本当の色を味わえる
こうした日常の喜びを取り戻すための手術です。
不安を感じたときこそ、「見えるようになった自分」を思い描いてみてください。私たちはその安心と感動を届けるため、万全の体制で手術に臨んでいます。
白内障手術の費用と保険適用

白内障手術は健康保険の対象ですが、選ぶ眼内レンズによって自己負担額が大きく変わります。ここでは、平均的な費用、利用できる制度、レンズごとの違いをまとめます。
平均費用と保険診療
保険診療(単焦点レンズ)
・費用目安:片眼あたり約4〜5万円(自己負担3割の場合)
・使用レンズ:単焦点眼内レンズ(乱視矯正付きトーリックレンズを含む)
※自己負担1割なら約1万5千円が目安です。
※乱視矯正付きレンズも条件を満たせば保険適用となります。
選定療養とは
「選定療養」とは、保険診療と自己負担を組み合わせて受けられる制度で、厚生労働省が認可した高機能レンズを希望する場合に利用します。
選定療養では、手術そのものは保険診療ですが、次の費用は自己負担になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 眼内レンズ費用 | 厚労省認可の多焦点・EDOFなど |
| 術前高度検査 | 乱視や角膜形状、瞳孔サイズなどの精密検査 |
| カウンセリング | 焦点距離の設計、見え方シミュレーション、生活設計の相談 |
| 術後チェック | 必要に応じた視機能評価・追加診察 |
高額療養費制度は保険診療部分のみが対象で、選定療養の追加費用には適用されません。
当院では、レンズの種類や焦点距離の設定、見え方のシミュレーションを丁寧に説明し、ライフスタイルに合わせた「視機能設計」を行います。選定療養は単なる「高機能レンズを選ぶ制度」ではなく、術後の生活を見据えたトータルサポートです。
自由診療
費用目安:片眼あたり約30万〜80万円(全額自己負担)
厚労省未認可のレンズを使用する場合や、フェムトセカンドレーザー手術を単焦点レンズで受ける場合は自由診療となります。手術・検査・薬剤を含め、費用はすべて自己負担です。
健康保険と高額療養費制度
- 健康保険:単焦点レンズ使用なら保険適用。3割負担で片眼約4〜5万円。
- 高額療養費制度:医療費が一定額を超えた場合、収入に応じた上限を超える分が払い戻されます。ただし、選定療養や自由診療の自己負担分は対象外です。
レンズと制度の比較
| 区分 | レンズ例 | 保険適用 | 自己負担 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 保険診療 | 単焦点(乱視矯正含む) | 〇 | 1〜3割 | 焦点は1か所。焦点距離を術前に設定。 |
| 選定療養 | 多焦点・EDOF(認可済) | 手術は保険適用 | レンズ代や追加検査は自己負担 | 見える範囲が広く、ライフスタイルに合わせやすい。 |
| 自由診療 | 未認可の多焦点・EDOFなど | × | 全額自己負担 | 最新設計や特殊レンズに対応。施設により費用差あり。 |
白内障手術は、単焦点レンズなら保険診療で自己負担は数万円程度に抑えられます。
より広い視界を求める場合は、選定療養で多焦点やEDOFレンズを選ぶことで生活の快適さが高まります。
費用・制度・見え方のバランスを理解し、医師と相談して自分に合ったレンズを選ぶことが、術後の満足度を左右するポイントです。
手術を「しない方がいい」ケースとは?

白内障があっても、いつでも手術が最善とは限りません。 基準になるのは「安全性」と「生活の質(QOL)」です。視力への影響が小さい、全身状態に配慮が必要、ほかの眼病が回復を妨げる――こうした場合は、急がず経過観察が適切なことがあります。
手術を控える主なケース
次のような状況では、まず見送りや慎重な検討が妥当です。
| ケース | 説明 |
|---|---|
| 視力低下が軽度 | 眼鏡調整で日常生活に支障がなければ、当面は手術不要。 |
| 全身状態にリスク | 心不全・脳梗塞直後・重度の認知症などは、安全性を最優先。 |
| ほかの眼疾患で改善が乏しい | 進行緑内障・加齢黄斑変性・重度網膜病変では、手術しても視力向上が限定的。 |
| 理解や意思の確認が困難 | 強い不安や理解の不十分さがある場合は、環境調整と説明を優先。 |
| 両眼同日希望だが高リスク | 強い不正乱視・角膜不正などは、片眼の結果を見てからもう一眼へ進めるのが安全。 |
タイミングを誤らないために
人工の眼内レンズは本来の水晶体とは性質が異なります。 老眼が軽い段階や、まだ自然な見え方が保たれている段階で早めに手術を選ぶと、「コントラストがやや落ちた」「近くは見えるが質感が違う」など、“見え方の質”の違いが気になることがあります。
「今の目で自然に見えている期間」も大切な資産。 焦らず、生活への影響と希望する見え方を天秤にかけて判断しましょう。
当院の方針
私たちは「手術をすること」自体を目的にしません。
- 十分な検査とカウンセリングを行い、今すぐ手術が必要かを共同で判断します。
- 生活スタイル・ご本人/ご家族の希望・既往歴を総合し、手術の価値と安全性を見極めます。
- 視力変化が緩やかで支障が少ない場合は、定期検査で見守る選択肢を提示します。
受診・相談の目安
次のような変化があれば、早めの相談が安心です。
最近、明るい場所でも見えづらい/眼鏡を替えても改善しない/左右で見え方に違和感がある/心臓・脳の病気を抱える/転びやすくなった、視野の欠けを感じる/認知症の進行で説明理解が難しい――こうした場合は、手術の是非を含めて慎重に評価します。
白内障手術は安全で有効ですが、「いつ」「どこまで改善を望むか」で最適解は変わります。
自然な見え方が保てている間は温存も価値ある選択。私たちは、“生活の質が確かに上がるか”を軸に、手術の適否とタイミングを一緒に決めていきます。
白内障手術後の経過と注意点

白内障手術は日帰りが可能な安全性の高い手術です。多くの方が翌日から通常の生活に戻れますが、眼の中に人工レンズを入れる手術であるため、感染や炎症を防ぐために段階的な行動制限が必要です。
術後の生活・行動の目安
当院では次のようなスケジュールを目安にご案内しています。個人差がありますので、医師の指示を優先してください。
| 行動・生活内容 | 再開の目安 | ポイント |
|---|---|---|
| スマホ・読書・テレビ | 翌日から | 目が疲れない範囲で徐々に慣らす |
| 事務作業・PC業務 | 翌日から | まぶしさや疲れがあれば休憩を |
| 洗顔・洗髪 | 4日目以降 | 水が眼に入らないよう注意、美容室等で眼に入らないように洗髪するのは可能 |
| メイク(特にアイメイク) | 1週間以降 | 感染リスクがあるため慎重に |
| 軽い外出・散歩 | 1週間以降 | 汗やほこりが入らないように |
| ヨガ・軽い体操 | 2週間以降 | 下を向く姿勢や強い力は控える |
| 水泳・スポーツ・重労働 | 1か月以降 | 水・汗・衝撃による感染や炎症を防ぐ |
食事や排泄、会話、近所への買い物など日常動作は翌日からほぼ問題ありません。ただし、眼をこすらない・汚れた手で触らないなど、清潔を保つことが大切です。
視力の回復と見え方
手術で濁った水晶体を取り除くことで視界が大きく改善します。
- 眼鏡をかければ9割以上の方が視力1.0以上まで回復します。
- 裸眼視力は「ピントの設定」や「乱視の有無」により個人差があります。
当院では、生活スタイルに合わせた焦点距離の設計や乱視矯正を事前に調整し、術後の見え方が快適になるよう配慮しています。
手術後は「見える喜び」をすぐに感じられる方が多い一方、明るさや色の鮮やかさに驚く方も少なくありません。
焦らず、無理をせず、少しずつ自分のペースで新しい見え方に慣れていくことが、快適な回復への近道です。
以下のようにまとめ直すと、情報量を保ちながらも流れが整理され、読みやすくなります。重複表現を減らし、見出しを統一しつつ「後悔の理由→対策→万一の場合の対応→まとめ」という順にしました。
よくある後悔・トラブル事例と対策

白内障手術後に「思っていた見え方と違った」と感じる理由は、術前に十分な説明やイメージができていない場合が多くあります。代表的なケースを整理します。
老視矯正レンズを選べばよかった
単焦点レンズで手術後、スマホや近くの作業に眼鏡が必要となり「多焦点にすればよかった」と感じる例です。
対策:単焦点でも焦点距離の設定や左右の度数を少しずらす「マイクロモノビジョン」など、裸眼で過ごしやすくする方法があります。
近くに合わせたら遠くが見えない
単焦点は一か所にしかピントが合わないため、近くに合わせると遠方がぼやけます。
対策:運転・読書・料理など、生活で重要な距離を具体的に共有し、希望する距離(例:3m先、パソコン距離)を明確にすることが重要です。
遠くは見えるが老眼がつらい
遠方に合わせると、読書やスマホには老眼鏡が必要になります。
対策:左右の焦点を変えるマイクロモノビジョンや多焦点レンズが選択肢となります。
強度近視なのに「手術後も近視で」と決められた
過去の近視歴だけで近方合わせにされた例です。
対策:近視・遠視どちらにも合わせられること、複数の設計があることを事前に説明してもらいましょう。
乱視が残って二重に見える
乱視補正の度数や軸がわずかにずれると、視界がにじんだり二重に見えることがあります。
対策:角膜の詳細解析データを基に、トーリックレンズや角膜切開位置を精密に調整することが大切です。
「遠くに合わせたはず」が1mしか見えない
設定より屈折値がずれる「屈折誤差」が原因です。
対策:遠くとは何メートルか、どこまで手前が見えるかを具体的に確認してから手術を受けます。
老眼は治ったが見え方が不自然
老眼改善だけを目的に早く手術を受けると、「近くも遠くも中途半端」な違和感につながることがあります。
対策:まだ自分の水晶体が十分に働いている場合は、手術時期を慎重に検討することが重要です。
後悔を防ぐためのポイント
- ピントの仕組みを理解:単焦点レンズは一か所しか焦点が合いません。遠・中・近のどこを優先するかを明確に。
- 具体的に希望を伝える:漠然と「遠くが見えるように」ではなく、「3m先」「パソコン距離」など具体的に相談。
- 生活スタイルに合わせて選択:最新レンズが必ず最良とは限りません。多焦点やEDOFも特徴を理解して選びましょう。
- 十分なカウンセリング:術後の見え方をシミュレーションし、医師とイメージを共有することが不可欠です。
満足できない場合の対応
見え方に違和感がある場合も「やり直しができない」わけではありません。医師と相談の上、次の方法が検討されます。
| 方法 | 内容・適応 | 注意点 |
|---|---|---|
| 眼内レンズ入れ替え | 度数の大きなズレや多焦点が合わない場合 | 手術後数週間〜数か月以内が望ましい |
| タッチアップレーシック/PRK | 近視・遠視・乱視の微調整 | 角膜が薄い場合は不可 |
まずは脳が新しい見え方に慣れていない可能性や、眼鏡で補える範囲かを丁寧に再評価することが大切です。
当院では高性能なエキシマレーザーを完備しているため、万が一の度数ズレにも精度の高い修正が可能です。
白内障手術は「濁りを取る」だけでなく、どのような見え方を得るかを設計する手術です。後悔を避けるには、術前に生活スタイルと希望する距離を具体的に共有し、レンズ特性を正しく理解すること。医師との十分な対話こそが、満足度の高い結果につながります。
よくある質問

Q1. 両眼の手術はどのように進めますか?片眼だけでも大丈夫ですか?
白内障手術は片眼ずつ行うのが基本です。
まず片眼を手術し、数日〜1週間ほど経過を見てからもう片眼を手術します。
こうすることで、1回目の結果を確認しながら、もう一方の眼の設計や度数を微調整できます。
片眼だけの手術で生活することも可能ですが、左右の見え方に差が出るため、以下のような対応が必要になる場合があります。
- 手術をしていない眼にコンタクトレンズを使用
- 視力バランスに合わせて生活スタイルを調整
Q2. 手術後もメガネは必要ですか?
レンズの種類とピントの設定によって異なります。当院では手術前カウンセリングの段階で焦点距離設計を綿密に行いますので、手術後に眼鏡使用が必要と考えられる場合には、あらかじめ作成していただくことをお勧めしています。
- 単焦点レンズ
- 遠くにピントを合わせると、近くを見るときに老眼鏡が必要。
- 近くに合わせると、遠くがぼやける。
- 手術前の眼の状態からや生活状況、術後のライフスタイルから、何をしている時間に眼鏡なしで生活をされたいかを考えたピントの設定がとても重要です。
- 多焦点レンズ/EDOFレンズ
- 裸眼で見える距離が広く、眼鏡の使用頻度は大幅に減ります。
- ただし、すべての距離が完璧に見えるわけではなく、コントラスト低下や光のにじみが出ることがあります。
また、乱視についてはトーリックレンズを用いて可能な限り修正いたしますが、乱視が最強度の場合は術後も眼鏡が必要なことがあります。
当院では、生活スタイルに合わせたピント設計とレンズ選定で、眼鏡の必要性を最小限に抑えています。
Q3. 白内障は再発しますか?二度目の手術は必要ですか?
白内障そのものが再発することはありません。人工レンズに置き換えた水晶体が再び濁ることはないためです。
ただし「後発白内障」と呼ばれる現象が、手術後半年〜数年以内に起こることがあります。これは水晶体を包んでいた膜(後嚢)が濁ってくるもので、視界が再びぼやけます。
治療は再手術ではなくレーザー治療(YAGレーザー)で行い、痛みもなく外来で数分程度で終了します。
白内障手術は、ただ視力を回復させるだけではなく、「どんな見え方で日常を過ごしたいか」を設計する手術です。
大切なのは、医師との十分な対話を通じて、自分のライフスタイルに合ったレンズ・タイミング・術後の過ごし方を選ぶこと。不安や疑問は、早めに相談すれば必ず解決への道が見えます。