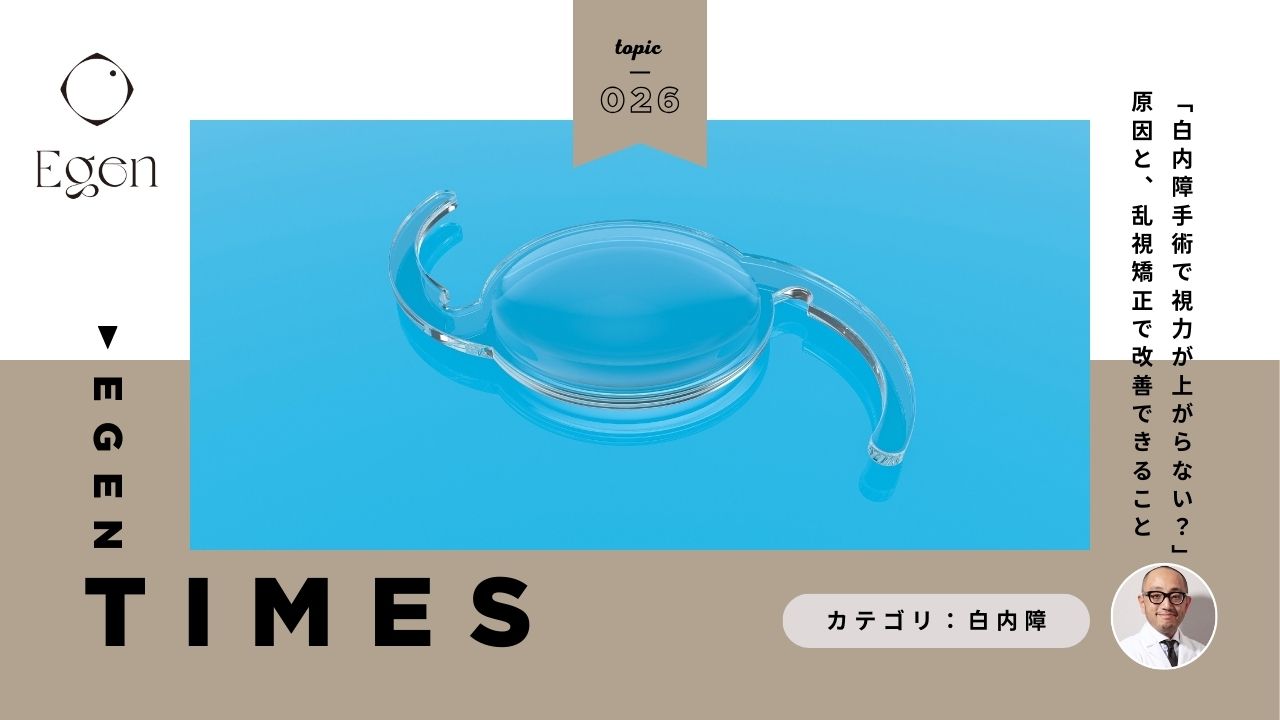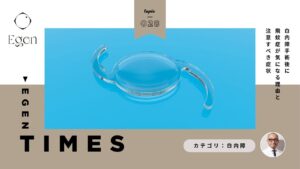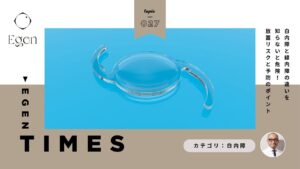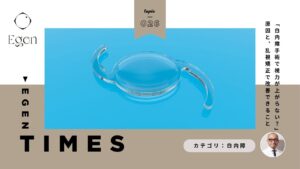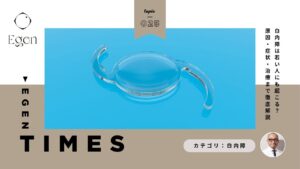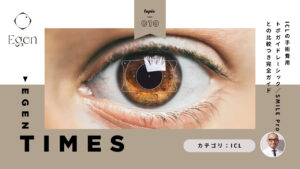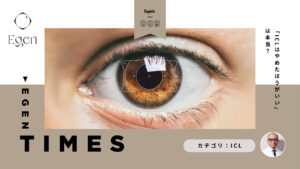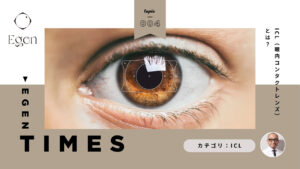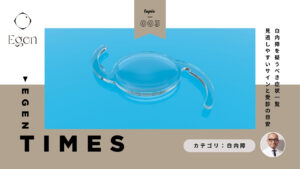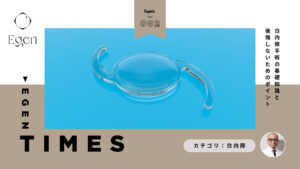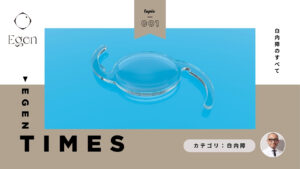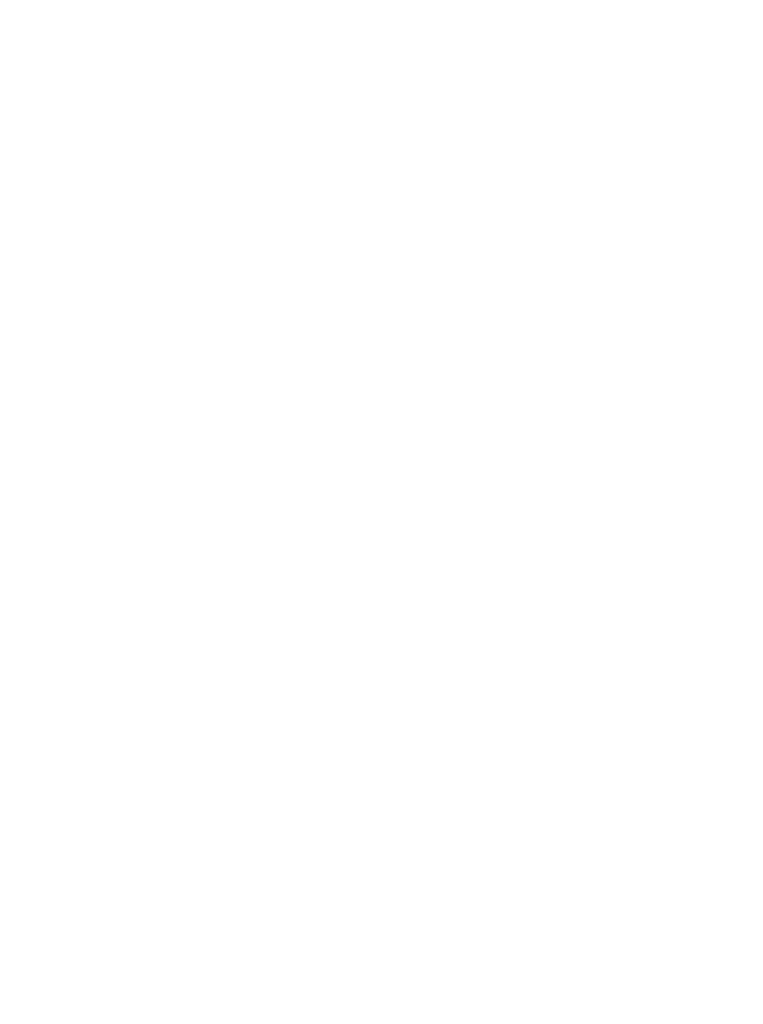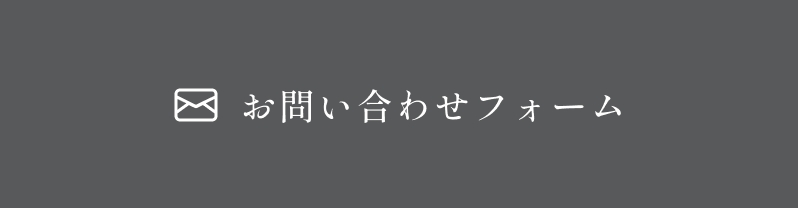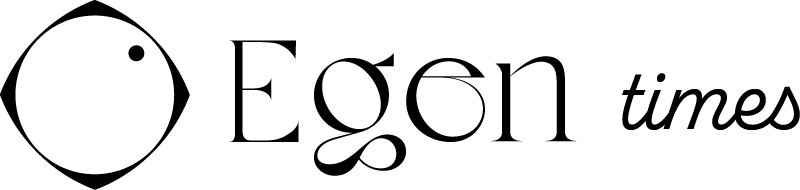白内障手術を受けたあと、「思ったよりスッキリ見えない」「視界がなんとなくにじむ」と感じていませんか? 手術は成功していても、「乱視の残り」や「レンズの度数ズレ」が原因で、視力の質が下がっているケースは決して少なくありません。
「せっかく手術したのに失敗?」と不安になる必要はありません。その見えにくさには明確な理由があり、多くの場合は改善が可能です。 この記事では、白内障手術後に視力が上がらない主な原因と、乱視矯正による解決策について、眼科専門医が分かりやすく解説します。
白内障と乱視は「別の病気」だけど密接に関係している

白内障と乱視の「違い」
白内障と乱視の違いをまず整理しましょう。
- 白内障:水晶体という眼の中のレンズが加齢などで濁ってしまい、視界がかすんだり、光がまぶしく見えたりする状態です。進行すると視力が大きく低下し、日常生活に支障をきたすことがあります。
- 乱視:カメラのレンズ(角膜や水晶体)が歪んでいる状態。「ピントが一点に合わず、二重に見える」状態です。
つまり、白内障と乱視はそれぞれ独立した病気ですが、どちらも視力に関わるため、皆さんが感じる“見えにくさ”としては重なって表れることがあります。
白手術後に乱視が出た」と感じる理由
実は、白内障が進行すると、水晶体が変形して「新たな乱視(水晶体乱視)」を作り出すことがあります。 これが、もともと持っていた「角膜の乱視」と偶然打ち消し合っていた場合、手術前は乱視を感じないことがあります。
しかし、手術で水晶体を取り除くと、打ち消し効果がなくなり、隠れていた角膜乱視が”表に出てくることになります。 患者様が「手術後に乱視になった気がする」と感じるのは、これが主な原因です。これは手術の失敗ではなく、隠れていた乱視が顕在化した生理的な現象です。
白内障が進行すると乱視になるケースとは
白内障によって水晶体の構造が変わると、以下のような乱視の変化が起こることがあります。
- 水晶体の一部が濁って光の通り道が偏ることで、像が歪んで見えるようになる。
- 水晶体全体が傾く・変形することで、乱視のような光のズレが生じる。
- 角膜に乱視がなくても、白内障の影響で乱視が出てくる場合もある。
こうした変化により、白内障が進行すると見え方が不安定になり、「見えづらさが増した」「メガネで矯正してもスッキリ見えない」といった症状が現れることがあります。
白内障手術で乱視は治せるのか?

結論から言うと、白内障手術のタイミングこそが、乱視を根治する最大のチャンスです。
「トーリック眼内レンズ」という選択肢
白内障手術では、濁った水晶体の代わりに人工の「眼内レンズ」を入れます。
このレンズに乱視矯正機能を持たせたものを「トーリックレンズ(Toric IOL)」と呼びます。
| レンズの種類 | 乱視矯正 | 特徴 |
| 単焦点レンズ | × なし | 一般的な保険適用のレンズ。乱視があると術後に眼鏡が必要。 |
| 単焦点トーリック | ○ あり | 保険適用で乱視も矯正できる。遠くがクッキリ見える。 |
| 多焦点トーリック | ○ あり | 選定療養や自由診療。遠近両用+乱視矯正で、眼鏡なしの生活を目指す。 |
どんな乱視でも治る?
治せない乱視: 角膜の表面がデコボコしている「不正乱視」。これはレンズでは矯正しきれないため、術後もハードコンタクト等が必要になることがあります。常の白内障手術と乱視矯正手術の違い
治せる乱視: 「直乱視(縦方向)」や「倒乱視(横方向)」などの規則的な乱視。
白内障手術では、濁った水晶体を取り除き、人工の眼内レンズ(IOL:Intraocular Lens)を挿入します。
この眼内レンズにはさまざまな種類があり、乱視があるかどうかによって「トーリックタイプ(乱視矯正あり)かノントーリックタイプ(乱視矯正なし)か」を選ぶ必要があります。
- 単焦点眼内レンズには「トーリック(乱視矯正あり)」と「ノントーリック(乱視矯正なし)」の2タイプがあります。
- 同様に、多焦点眼内レンズや焦点深度拡張型レンズ(EDOF)にも、トーリックとノントーリックの両方が存在します。
つまり、乱視矯正の有無は「レンズの基本構造(単焦点、多焦点、EDOF)」とは別に選ぶ要素であり、すべてのレンズタイプで乱視矯正可能なものと不可能なものがあるということです。
乱視は年を取るとひどくなる?
加齢により角膜のカーブや水晶体の形が少しずつ変化し、乱視の量や方向が変わることがあります。特に白内障の進行とともに水晶体が傾いたりゆがんだりすることで、新たに乱視が加わることもあり、「年を取ると乱視が強くなる」と感じる方が出てきます。
乱視を直す方法はありますか?
白内障が無い方の手段としては、
- 眼鏡やコンタクトレンズによる矯正
- レーシックやPRKなどの角膜矯正手術
などがあります。
白内障がある場合はまず水晶体の交換が必要となるため、最初の白内障手術時に乱視も同時に矯正することが手術後の視力を向上させる最も良い方法です。
手術後に「裸眼視力が上がらない・にじむ」3つの原因

白内障手術後になぜ乱視が残る?
白内障手術後に「乱視が出てきた」「手術前より見えにくい」と感じる方は少なくありません。その原因は、以下の3つが代表的です。
- 手術によって生じる惹起乱視(SIA)
- 水晶体乱視の消失によって、もともとの角膜乱視が顕在化する
- トーリック眼内レンズの軸ずれによる矯正効果の低下
これらはすべて、医療的に予測・説明可能な現象であり、異常や失敗ではありません。それぞれ詳しく見ていきましょう。
①手術による角膜の形状変化が原因(惹起乱視)
手術では角膜に小さな切れ込みを入れます。この傷が治る過程で、角膜の形がわずかに変わり、新たな乱視(惹起乱視)が生じることがあります。 ※熟練した医師は、これを計算に入れて手術計画を立てますが、治癒力には個人差があるため完全にゼロにすることは困難です。
②手術前検査での角膜乱視評価不足
白内障が進行した水晶体は、形状が不均一になったり傾いたりして水晶体由来の乱視を生じることがあります。
これが、もともと存在していた角膜乱視と偶然に打ち消し合っていた場合、術前には乱視をほとんど自覚していなかったこともあります。
しかし、白内障手術で水晶体を取り除くとその打ち消し効果が消失し、角膜乱視が単独で顕在化するため、患者は次のように感じます。
「手術前は乱視なんて言われたことなかったのに、手術後に乱視が出てきた…」
これは誤解ではなく、術前に水晶体が“乱視補正のような役割”をしていたためです。
こうした視覚の変化は、術後に乱視が新たに“加わった”というより、もともとあった乱視が“見えるようになった”という表現の方が正確です。手術前に正しく角膜乱視を評価することが手術の成功につながります。
③トーリック眼内レンズの軸ずれによる影響
乱視を矯正する目的で使用されるトーリック眼内レンズは、乱視の方向(軸)に正確に合わせて挿入されます。
しかし、術後にこのレンズがわずかに回転すると、乱視の矯正効果が著しく損なわれることがあります。
- 5度の回転 → 矯正効果が約15%減少
- 10度の回転 → 約30%減少
- 30度以上 → 矯正効果はほぼゼロ
このため、トーリックIOLを使用する場合は、術前の正確な軸計測・挿入時の高精度な位置合わせ・術後の回旋予防が非常に重要です。
レンズが回転しやすい眼内環境(深い前房、弛緩したチン小帯など)では注意が必要です。
乱視=白内障手術の失敗?
乱視が残る事すべてが失敗とは言えません。術後に残る乱視には様々な理由が他にもありますので、なぜ乱視が残っているのかを正しく理解し、対策を考えることも必要です。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 惹起乱視(SIA) | 手術操作による角膜変形で新たな乱視が生じる |
| 水晶体乱視の消失 | 角膜乱視との打ち消し効果がなくなり、乱視が表に出る |
| トーリックIOLの回旋 | 数度の軸ずれで矯正効果が大幅に減少する |
術前検査、切開位置の選定、レンズ選択・固定のすべてが術後の見え方に大きく関わります。
当院では、これらの要因を総合的に評価し、乱視のリスクを最小限に抑える設計と説明を徹底しています。
白内障手術後に乱視が残ってしまった場合の対処法

乱視はまず術前に評価し、矯正をしっかり行うことがファーストステップ
白内障手術を受ける際には、術前に詳しい検査を行い、角膜の形状や水晶体の状態から乱視の有無と程度を正確に把握します。
その結果、矯正が必要と判断された場合には、乱視矯正用の眼内レンズ(トーリックレンズ)を用いることで、乱視を同時に治療することが可能です。
また、手術によって生じるわずかな乱視(惹起乱視)についても、経験のある医師であれば事前に予測し、レンズ度数の設計に反映させることが一般的です。
したがって、「乱視が残る=手術計画が不十分だった」ということではありません。
それでもごく一部の方では、術後に乱視が残ったり、見え方に違和感を感じたりするケースがあるのも事実です。
乱視が残った場合の主な対処法
1.メガネで補正する(最も一般的)

最も基本的で安全な方法が、乱視度数を加えたメガネの使用です。
- 軽度〜中等度の乱視なら十分に見え方を改善できます
- 眼鏡処方は、術後の視力が安定してから行います(通常1か月以降)
ただし、強い乱視や左右差がある場合には、メガネでの補正が合わないと感じる方もいます。
2.コンタクトレンズでの補正

- トーリックタイプのソフトコンタクトや、ハードコンタクトを使うことで、乱視をより精密に補正できます。
- 不正乱視が強い場合には、ハードコンタクトの方が有利なことがあります。
コンタクトは視力の質を高められますが、遠近両用コンタクトレンズにはトーリックレンズがないので、単焦点眼内レンズを挿入された場合には、コンタクトレンズと眼鏡の併用が必要です。
3.眼内レンズの回転修正(再手術)
術後にトーリックレンズが回転してしまった場合は、早期であれば再手術で軸を戻すことが可能です。
- 多くは術後1か月以内であれば対応可能
- レンズが安定する前であれば、比較的簡便に行える手技です
回転しているかどうかは、簡単な検査で確認できますので、見え方に違和感があれば早めにご相談ください。
4.レーシック(レーザー)手術で角膜を整える(タッチアップレーシック)
「裸眼で過ごしたい」という強い希望がある場合、術後にレーシック等のレーザー手術を行い、残った乱視(角膜の歪み)を削って微調整する方法があります(※自費診療となります)。
5.眼内レンズの交換(IOL交換)
回転修正が難しい場合や、そもそも乱視度数の設定が合っていなかった場合には、レンズそのものを交換する選択肢もあります。
- 他の方法で補正が難しい場合に検討されるステップです
- 時間が経っている場合や、眼内の癒着が強い場合は難易度が高くなります
術前検査が正確でも、想定外の反応をする眼もあるため、全例で完全な予測は困難であることも現実です。
乱視は手術前になかったのに、なぜ術後に出てくるの?
中には「術前に乱視はないと言われたのに、手術後に眼鏡が必要になった」という声もあります。
実際には、術前に角膜乱視が軽度で、水晶体乱視とちょうど打ち消し合っていた場合、検査では目立たず「乱視なし」と判断されることがあります。
しかし白内障手術で水晶体を取り除くと、水晶体乱視が消え、角膜乱視だけが“表に出る”ため、術後に乱視が目立つように感じることがあります。
これは診断ミスではなく、手術による構造の変化によって生じるごく自然な現象です。
手術後しばらくしてから見えにくくなったのはなぜ?
術後すぐはよく見えていたのに、数週間〜数か月してから「なんとなくぼやけてきた」と感じることがあります。
この原因としては、下記のものなどが考えられます。
- トーリックレンズがゆっくりと回転してしまった
- 角膜の治癒過程で乱視がわずかに変化してきた
- 後発白内障(後嚢混濁)が起きた
後発白内障についてはYAGレーザーで簡単に治療できますので、違和感が続く場合は早めに眼科を受診しましょう。
乱視矯正用レンズの選び方

トーリックレンズとは?
トーリックレンズは、レンズに乱視矯正の度数(円柱度数)が組み込まれたものです。
角膜乱視が一定以上ある方に用いられ、術後に裸眼での見え方をより快適にすることができます。
- 単焦点レンズにも「トーリックタイプ」があり、これは保険適用内で使用できます。
- 一方、多焦点レンズ(遠近両用)やEDOF(焦点深度拡張型)にもトーリックタイプが存在し、こちらは選定療養または自由診療で提供されます。
※つまり、「トーリック=特殊な高額レンズ」ではなく、目的と制度に応じて選ばれる乱視矯正機能とご理解ください。
レンズの適応条件と選び方
トーリックレンズを使用するには、事前に精密な検査が必要です。
適応かどうかは以下のポイントで決まります。
| 評価項目 | 内容 |
| 角膜乱視の強さ | 通常は0.75D以上が目安(症状や生活への影響によって変わります) |
| 角膜乱視の軸 | 乱視軸が安定しているかどうか |
| 角膜の形状 | 円錐角膜や瘢痕がある場合は適応外 |
| 術後にレンズが回転しにくい構造 | 眼内の構造・チン小帯の状態なども考慮 |
費用について:乱視矯正は高くない?

「乱視用レンズは高いのでは?」と心配される方が多いですが、現在は制度が変わっています。
保険診療で使える「トーリックレンズ」
実は、単焦点のトーリックレンズ(乱視用)は、通常のレンズと同じく「健康保険」が適用されます。 追加費用なしで乱視矯正が可能ですので、適応がある方には積極的に使用が推奨されます。
多焦点レンズ(老眼対策)の場合
「遠近両用+乱視矯正」をご希望の場合は、「選定療養」または「自由診療」となり、追加の自己負担が発生します。
自由診療: 全額自費
選定療養: 手術代(保険)+ レンズ代の差額(自費)
トーリックレンズ(乱視矯正レンズ)の費用と保険の違い
乱視を矯正できるトーリックレンズには、保険で使えるものと保険外のものがあります。
| レンズの種類 | 保険適用 | 想定費用(片眼) | 特徴 |
| 単焦点(非トーリック) | ○ | 5万円(3割負担) | 保険内で一般的に使われる |
| トーリック単焦点 | ○ | 5万円(3割負担) | 保険内で乱視矯正が可能 |
| 多焦点(非トーリック) | ×(選定療養または自由診療) | 30〜50万円(選定療養) 30〜80万円(自由診療) | 遠方〜近方まで幅広く見える設計 |
| トーリック多焦点・EDOF | ×(選定療養または自由診療) | 上記に+5〜15万円程度追加が必要なことも | 乱視も矯正できる多焦点/焦点深度拡張型 |
※費用は施設ごとに異なりますが、保険適用の白内障手術の場合ノントーリックかトーリックかは関係なく、価格は同一です。
高額療養費制度は使える?
保険診療に該当する白内障手術では、「高額療養費制度」を使うことができます。これは、1か月あたりの自己負担額が一定額を超えた場合に、超えた分が後日払い戻される制度です。
保険診療の範囲内であれば、トーリック単焦点レンズによる乱視矯正も自己負担は3割です。さらに、年齢や収入によっては「高額療養費制度」が使えるため、1か月あたりの自己負担額に上限が設けられ、実質の支払額が1〜2万円台に抑えられることもあります。このため、保険診療内での乱視矯正は、比較的負担の少ない方法といえます。ただし、多焦点やEDOFタイプのレンズを使った自由診療や選定療養の部分には適用されません。そのため、「自由診療でかかる費用」は高額療養費の対象外となる点には注意が必要です。
まだある白内障手術で視力が上がらない理由とは?

白内障手術を受けた後、「思ったほどよく見えない」「視界がぼやける」と感じることがあります。手術自体は成功していても、視力の質や満足度が想定を下回る原因は「乱視」だけではなく、いくつか存在します。
ここでは、代表的な3つの原因を整理してご説明します。
屈折誤差(ピントのズレ)が起きている
白内障手術では、どの距離にピントを合わせるか(遠く、中間、近く)を事前に医師と相談して決めます。
しかし、以下のような理由で術後にその焦点がずれると、思ったような見え方にならないことがあります。
- 眼内レンズの度数計算にわずかな誤差があった
レンズの度数は、術前の角膜のカーブや眼球の長さ、前房深度(角膜と水晶体の間の距離)などをもとに計算されます。術後の眼の状態がわずかに予測と異なるだけでも、焦点が少しずれることがあります。加えて手術前検査の精度がずれてしまうと、誤差を生じてしまう原因となりますので、術前検査がとても重要です。 - 見たい距離と実際の生活の距離が違った
たとえば「遠くがよく見えるように」と焦点を設定しても、実際の生活ではパソコンや料理など中間距離の作業が多く、見えづらさを感じることがあります。これは医学的には「誤り」ではなく、患者さんの生活スタイルとのミスマッチが原因となります。
眼底や黄斑の病気があった
白内障手術をしても視力が改善しない場合、網膜や視神経の疾患が隠れていることがあります。
- 加齢黄斑変性
黄斑部がダメージを受けていると、視力そのものが出にくく、ゆがんで見えることもあります。 - 糖尿病網膜症・緑内障
白内障以外の病気が原因で視力が落ちていると、手術しても見え方が改善しない可能性があります。
これらの疾患は、術前の精密な眼底検査である程度把握できますが、白内障が濃いと検査が難しいこともあります。術後に初めて病気が見つかるケースも少なくありません。
白内障手術は何回までできる?

基本的には一度きりの手術
白内障手術は、濁った水晶体を取り除いて人工の眼内レンズ(IOL)を挿入する治療です。基本的に白内障手術は片眼につき一度きりの手術で完了し、同じ眼に何度も白内障手術を繰り返すということはありません。
ただし、手術後に見え方に問題が生じた場合や、眼内レンズに関連するトラブルがあった場合には、例外的に再手術やレンズの入れ替え(IOL交換)が行われるケースもあります。
再手術や追加処置が必要になるケースとは?
以下のような状況では、術後に再度処置や手術が必要になることがあります。
眼内レンズの度数誤差・屈折誤差
眼内レンズの度数計算には術前の詳細なデータを用いますが、わずかな誤差が生じることがあります。その結果、予定していた見え方と異なる「屈折誤差」が残ってしまうことがあります。
このような場合には、眼鏡やコンタクトレンズでの矯正が基本ですが、誤差が大きく、日常生活に支障がある場合には、眼内レンズの再計算と交換手術が検討されることもあります。
乱視矯正が不十分だったケース
トーリック眼内レンズを使用して乱視を矯正する際、レンズの位置がずれると矯正効果が落ちてしまいます。特に軸の回転が起こると、乱視が十分に矯正されず、再手術での位置修正やレンズ交換が必要となることがあります。
また、トーリックレンズでは矯正が困難な「不正乱視」があった場合、予想外に見えにくさが残ることもあり、術後に再評価と対処が求められるケースもあります。
老視矯正レンズが合わなかったケース
老視矯正レンズのうち、とくに複数の距離に焦点が合うよう設計されている多焦点レンズは、時に以下のような問題を生じることがあります。
- 思っていた以上にコントラストが低下した
- ハロー・グレア(光のにじみやまぶしさ)が強く生活に支障がある
- 脳の順応がうまくいかず、複数の焦点をうまく使いこなせなかった
こうした症状がどうしても改善しない場合、単焦点レンズへの入れ替えを希望される方もいます。
後発白内障
手術で水晶体を包んでいる「後嚢(こうのう)」を残すため、数ヶ月から数年の経過でこの膜が濁ってくることがあります。これは「後発白内障」と呼ばれ、視界が再びかすむ原因となりますが、YAGレーザーという処置で簡単に治療可能で、再手術には該当しません。
レンズ交換はできる?どれくらいの期間まで可能?
技術的には、眼内レンズを取り出して交換することは可能です。ただし、注意点もあります。
- 時間が経つと、レンズと眼内組織が癒着し、交換手術が難しくなる
- 再手術は通常の白内障手術より技術的に難しくリスクも費用も高い
そのため、レンズ交換は慎重な判断が必要な「特例措置」と考えるべきことで、術前の丁寧なカウンセリングとレンズ選択が非常に重要です。
白内障手術は「見え方」をリセットする好機

白内障手術は大チャンスでもある
白内障手術では、濁った水晶体を取り除いて人工の眼内レンズ(IOL)に置き換えるため、水晶体に由来する乱視(水晶体乱視)は原則として取り除かれることになります。
このタイミングで、角膜に由来する乱視(角膜乱視)もあらかじめ評価しておけば、乱視矯正機能のあるトーリック眼内レンズを選ぶことで、乱視の改善を同時に図ることが可能です。
つまり白内障手術は、「見え方の質」を治療する大きなチャンスでもあるのです。
レンズ選びが結果を大きく左右する
乱視矯正の有無にかかわらず、白内障手術では人工レンズの種類が複数あり、どのタイプを選ぶかによって術後の見え方や生活の快適さが変わってきます。
レンズの種類と乱視矯正
- 単焦点レンズ(ノントーリック)
→ 乱視矯正なし。軽度乱視であれば眼鏡で補正可能な場合に選択。 - 単焦点トーリックレンズ
→ 角膜乱視を同時に矯正可能。保険適用(条件あり)。 - 多焦点/焦点深度拡張型レンズ(EDOF)
→ 遠くも近くも見える設計。トーリックタイプもあり、乱視矯正と老視矯正を同時に行える。
※ただし、不正乱視(角膜の表面が歪んでいるタイプの乱視)は眼内レンズでは矯正が困難なため、メガネやレーシック手術などで対応する必要があります。
医師の判断と術前検査がカギ
術前には、乱視の種類・方向・程度だけでなく、惹起乱視(手術によって新たに生じる乱視)の予測、水晶体が持っていた乱視の打ち消し効果の評価なども含めて、精密な検査と設計が必要です。
また、同じ「乱視」といっても、直乱視・倒乱視・斜乱視でレンズ選びや切開位置も変わってくるため、経験と技術のある眼科医の判断が重要になります。
術後の視力トラブルは放置しないで
白内障手術のあとに「思ったより見えにくい」「視界がぼやける」と感じる場合、原因が乱視の残存や眼内レンズのずれ、あるいは黄斑疾患などにある可能性もあります。
そのまま我慢せずに、必ず術後の定期検診や相談の機会を活用しましょう。
見え方の不調に対しては、
- メガネやコンタクトによる補正
- レンズの回転や再固定手術
- レンズ交換(ごく稀)
など、状況に応じた対応策があります。
白内障手術は「眼の全部リセット」ではない
白内障手術によって視力の回復は期待できますが、すべての見えにくさが完全に解消されるわけではありません。
もともとの角膜のゆがみ(不正乱視)や、網膜・視神経の疾患など、眼全体の状態が見え方を決める要素となります。
また、ピントを合わせる距離(遠方/中間/近方)は手術前に医師と相談して決めますが、「実際に生活してみたら思ったより近くが見えにくい」「老眼鏡が必要だった」など、術前と術後の生活感覚にギャップを感じる方もいます。
このような認識のズレは手術の失敗ではなく、事前の説明や理解不足によって生じる誤解であることも多いため、手術前のカウンセリングが非常に重要です。
よくある質問
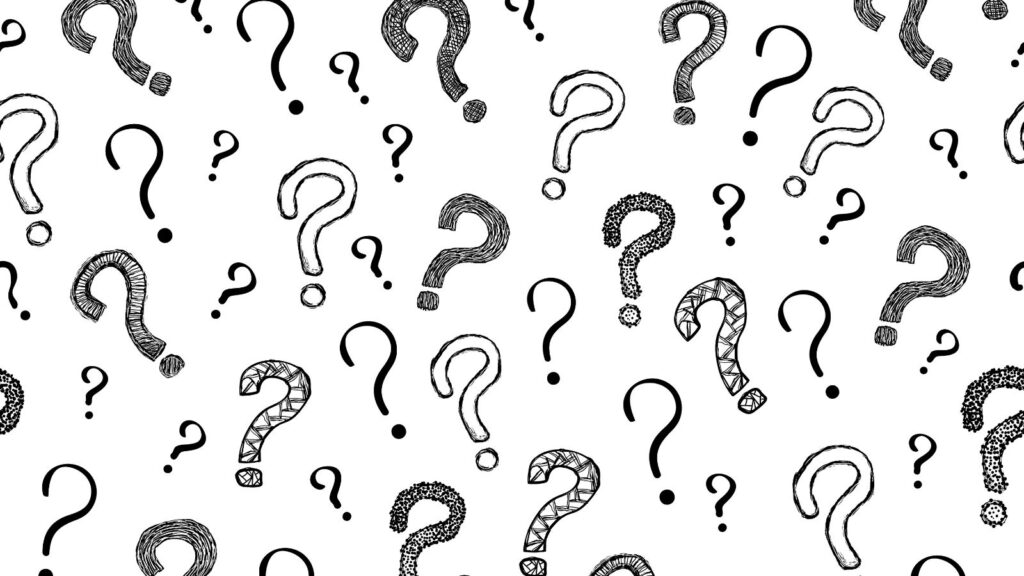
失敗とは限りません。白内障手術後に視界がぼやける原因のひとつとして「乱視が残っている」ことがあります。
とくに角膜に由来する乱視が強く残っている場合、遠くも近くもピントが合いづらく、にじんで見える・ぼやけるといった症状が出やすくなります。
ただし、ぼやけの原因は乱視だけとは限りません。
たとえば以下のようなケースでも同様の見えにくさを感じることがあります。
・多焦点レンズや焦点深度拡張型レンズによるコントラスト感度の低下
・網膜や黄斑に異常がある場合(例:加齢黄斑変性、糖尿病網膜症)
・後発白内障(術後数ヶ月〜数年後に発生)
見えにくさが続く場合は、原因を特定するために再検査を受けることが大切です。
基本的には半永久的に使用できるものです。レンズ自体が経年劣化することはほとんどありません。
ただし、以下のような理由で術後に乱視の再出現や見え方の変化が起きる可能性はあります。
・加齢による角膜形状の変化(特に80代以降で直乱視→倒乱視への変化)
・トーリックレンズの回転による乱視矯正効果の低下
・術後に新たに生じた不正乱視(角膜のゆがみ)
このような場合でも、眼鏡やコンタクトで補正が可能なことが多いため、定期的な検診が重要です。
はい、使えます。白内障が進行していなくても、「見えづらさ」や「生活の不便さ」を強く感じている場合、保険診療・選定療養・自由診療を含めた手術時期の柔軟な判断が可能です。
角膜乱視が強く、裸眼視力に大きな影響がある場合は、白内障の進行度にかかわらずトーリックレンズの使用を検討する価値があります。
ただし、手術のタイミングは水晶体の濁りの程度と日常生活への支障のバランスを見て判断されます。
そのため、術前にしっかりと検査を行い、乱視の種類や程度を正確に評価した上で、最適なレンズを選択することが大切です。
乱視矯正レンズ(トーリックIOL)の場合、軸のズレにより矯正効果が弱まることがあります。ズレが大きい場合は、再手術での修正が検討されます。
手術による角膜切開やレンズの固定位置などが原因で、新たに生じる乱視が出ることがあります。ただし、これは術前に予測して対応できる範囲内であることが多いです。
はい、多焦点レンズやEDOFレンズにもトーリックタイプ(乱視矯正タイプ)があります。適応がある場合には乱視矯正と老視矯正を同時に行うことが可能です。
白内障手術は、単に濁りを取るだけでなく、長年付き合ってきた「乱視」とお別れできる絶好のチャンスです。
「手術したのに見えにくい」という場合も、原因を特定すれば改善策は必ずあります。 大切なのは、術前の精密な検査と、術後の違和感を正直に医師に伝えることです。 ご自身の目に最適なレンズと微調整で、クリアな視界を取り戻しましょう。